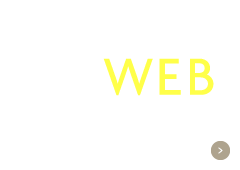目次
こんにちは!ほほえみ歯科りんくう院です!

歯垢(プラーク)と歯石の違い
はじめに
私たちの口腔内には様々な細菌が存在しており、それらは時に歯垢(プラーク)や歯石となって歯の健康を脅かします。歯科医院での定期検診やクリーニングでは、「歯垢をしっかり除去しましょう」「歯石がついていますね」といった言葉をよく耳にするかもしれません。しかし、この二つは同じものでしょうか?実は、歯垢と歯石は形成過程や性質、除去方法など、多くの点で異なります。本稿では、歯垢(プラーク)と歯石の違いについて詳しく解説し、それぞれの予防法や対策についても触れていきます。
歯垢(プラーク)とは
歯垢の定義と構成要素
歯垢(プラーク)とは、歯の表面に形成される無色透明か薄い黄白色の粘着性のある細菌の塊です。主に口腔内の細菌、食物残渣、唾液中のタンパク質、多糖類などが混ざり合って形成されます。歯垢は肉眼では見えにくいですが、歯の表面を舌で触ると、ざらついた感触として感じることができます。
歯垢の主な構成要素は以下の通りです:
- 口腔内細菌:主にレンサ球菌(ミュータンス菌など)や桿菌などの様々な種類の細菌
- 細菌外多糖体:細菌が産生するねばねばとした物質で、細菌の歯面への付着を助ける
- 唾液由来のタンパク質
- 食物残渣
歯垢の形成過程
歯垢の形成は、歯を磨いた直後から始まります。その過程は以下のような段階を経ます:
- ペリクル形成:歯を磨いた後、数分以内に唾液中のタンパク質が歯の表面に吸着し、「獲得被膜(ペリクル)」という薄い膜を形成します。
- 初期細菌の付着:ペリクルが形成されると、特定の細菌がこの膜に付着し始めます。最初に付着するのは主にレンサ球菌などの好気性菌です。
- 細菌の増殖と成熟:付着した細菌は分裂して増殖し、また新たな細菌も次々と付着します。時間が経つにつれて嫌気性菌も増え、複雑な細菌叢を形成します。
- バイオフィルムの完成:約24〜48時間で、歯垢は成熟したバイオフィルムとなります。このバイオフィルムは細菌が作り出す多糖体によって保護され、外部からの影響を受けにくくなります。
歯垢の危険性
歯垢は以下のような口腔トラブルの原因となります:
- 虫歯(齲蝕):歯垢中の細菌は糖分を代謝して酸を産生し、その酸が歯のエナメル質を溶かして虫歯を引き起こします。
- 歯肉炎:歯と歯肉の境目に蓄積した歯垢中の細菌が歯肉に炎症を引き起こします。症状としては、歯肉の赤み、腫れ、出血などが見られます。
- 口臭:歯垢中の細菌が産生する揮発性硫黄化合物などが口臭の原因となります。
- 歯周病への進行:放置された歯肉炎は、やがて歯を支える骨にまで影響を及ぼす歯周病へと進行する恐れがあります。
歯石とは
歯石の定義と構成要素
歯石は、歯垢が石灰化(ミネラル化)したものです。唾液中のカルシウムやリン酸塩などのミネラルが歯垢に沈着して硬化し、形成されます。歯石は黄色や茶色、灰色などの色を呈し、硬い岩のような性質を持っています。
歯石の主な構成要素は以下の通りです:
- ミネラル成分:主にリン酸カルシウム、炭酸カルシウムなど
- 有機質成分:歯垢由来の細菌やその代謝産物
- 色素成分:食べ物や飲み物、タバコなどに含まれる色素
歯石の形成場所と種類
歯石は主に以下の2種類に分類されます:
- 歯肉上歯石(supragingival calculus): 歯肉の縁より上の歯の表面に形成される歯石です。主に唾液の影響を受けやすい場所、特に唾液腺の開口部近くの歯(下顎前歯の舌側や上顎大臼歯の頬側)に多く見られます。黄色や白色を呈することが多く、比較的軟らかめです。
- 歯肉下歯石(subgingival calculus): 歯肉の縁より下の歯周ポケット内に形成される歯石です。歯肉上歯石と比べて硬く、濃い茶色や黒色を呈することが多いです。歯周病の進行に大きく関わります。
歯石の形成過程
歯石の形成過程は以下のような段階を経ます:
- 歯垢の蓄積:まず、歯の表面に歯垢が形成されます。
- ミネラルの沈着:唾液や歯肉溝滲出液に含まれるカルシウムやリン酸塩などのミネラルが歯垢内に沈着します。
- 結晶核の形成:沈着したミネラルが結晶核を形成し、徐々に成長していきます。
- 石灰化の進行:結晶化が進むにつれて歯垢は硬化し、歯石となります。この過程は早ければ24〜48時間で始まり、約12日ほどで完成します。
歯石の危険性
歯石は以下のような問題を引き起こします:
- 歯垢の温床:歯石の表面はざらざらしており、新たな歯垢が付着しやすくなります。
- 歯肉炎や歯周病の促進:歯石は物理的な刺激となって歯肉を傷つけるだけでなく、細菌の温床となることで炎症を悪化させます。
- 審美的問題:特に前歯部の歯石は見た目にも悪影響を及ぼします。
- 口臭の増強:歯石に付着した細菌は口臭を強める原因となります。
歯垢と歯石の主な違い
物理的特性の違い
- 硬さ:
- 歯垢:柔らかく、粘着性があり、歯ブラシで除去可能
- 歯石:硬く固着しており、歯ブラシでは除去できない
- 色と見た目:
- 歯垢:無色透明または薄い黄白色で、歯面を染め出さないと見えにくい
- 歯石:黄色、茶色、灰色など色素を含み、目視で確認できる
- 形成速度:
- 歯垢:歯磨き後数時間で形成が始まり、24〜48時間で成熟
- 歯石:歯垢の石灰化には通常1〜2週間程度かかる
除去方法の違い
- 歯垢の除去:
- 日常的な歯磨き、フロス、歯間ブラシなどのセルフケアで除去可能
- プラークコントロールは自宅で毎日行うことができる
- 歯石の除去:
- 歯科医院での専門的なクリーニング(スケーリング)が必要
- 超音波スケーラーや手用スケーラーなどの専用器具を使用
- 一度形成された歯石はセルフケアでは除去できない
予防と対策
歯垢の予防法
- 正しい歯磨き:
- 1日2回以上、特に就寝前には丁寧に歯磨きを行う
- 適切な歯ブラシ(柔らかめ〜中程度の硬さ)と歯磨き粉を使用
- 歯と歯茎の境目や、かみ合わせ面もしっかり磨く
- 補助的清掃用具の使用:
- デンタルフロスで歯間の歯垢を除去
- 歯間ブラシで歯間部のより効果的な清掃を行う
- タフトブラシで磨きにくい部分を重点的に清掃
- 食生活の工夫:
- 砂糖を多く含む食品や飲料の摂取を控える
- 食事と食事の間の間食を減らす
- キシリトール配合のガムを活用する
- 定期的な歯科検診:
- 3〜6ヶ月に一度、歯科医院で歯垢の状態をチェック
- 必要に応じてプロフェッショナルクリーニングを受ける
歯石の予防法
- 徹底した歯垢コントロール:
- 歯石は歯垢から形成されるため、歯垢を効果的に除去することが最大の予防法
- 定期的な歯科医院でのクリーニング:
- 歯石の形成しやすさには個人差があるため、自分に合った間隔(通常3〜6ヶ月)で専門的なクリーニングを受ける
- 抗歯石成分を含む歯磨き粉の使用:
- ピロリン酸塩や亜鉛塩などの抗歯石成分が配合された歯磨き粉は、ミネラルの結晶化を阻害する効果がある
- 唾液の活用:
- 唾液には自浄作用やミネラルバランスを整える働きがあるため、十分な水分摂取や噛みごたえのある食品を摂取して唾液分泌を促進する
歯科医院での対応
プロフェッショナルケア
- 歯垢染色:
- 染め出し液で歯垢を可視化し、磨き残しをチェック
- 効果的な歯磨き指導に活用
- スケーリング:
- 専用器具を使用して歯石を除去
- 超音波スケーラーや手用スケーラーを使い分ける
- ルートプレーニング:
- 歯周ポケット内の歯石や感染した歯根面を清掃・滑沢化
- 歯周病治療の重要なステップ
- PMTC(Professional Mechanical Tooth Cleaning):
- 専門的な機械的歯面清掃
- 特殊な器具や研磨剤を用いて、歯垢や着色を徹底的に除去
まとめ
歯垢と歯石は、形成過程、物理的特性、除去方法など多くの点で異なります。歯垢は日常のセルフケアで除去できますが、歯石は一度形成されると専門的な処置が必要となります。
健康な口腔環境を維持するためには、日々の丁寧な歯磨きとデンタルフロスなどの補助的清掃用具の使用が基本です。また、定期的に歯科医院を受診し、プロフェッショナルケアを受けることで、歯垢の蓄積を防ぎ、歯石の形成を予防することができます。
口腔内の健康は全身の健康にも関わります。歯垢と歯石の違いを理解し、それぞれに適した予防・対策を行うことで、生涯にわたって健康な歯と歯茎を維持していきましょう。歯と口の健康は、美しい笑顔と快適な食生活を支える大切な基盤なのです。
泉南市おすすめ、ほほえみ歯科りんくう院で、怖くない!痛くない!治療を受けてみませんか?
是非、ご来院ください。